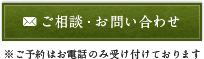きもののお話
琉球紅型
沖縄の紅型は京友禅、加賀友禅、江戸小紋と並ぶ代表的な伝統染色です。しかし、その鮮やかな配色と柄ゆきは独特で、明らかに他の染物とは異なる趣です。紅型の紅とは、赤や朱など特定の色を意味するのではなく、沖縄の言葉で色の事を言い、型は模様のことを差します。つまり紅型とは色模様という意味の言葉なのです。
紅型はもともと琉球王朝時代においては、士族階級以上の婦人たちの打掛けとして儀式や礼祭などに使用される特別なものでした。その歴史は古く、中世のなかば中国から入ってきた「形附(かたちき)」と呼ばれる摺込型染が源流とされ、15世紀頃の作と伝えられる染色品も残されています。この時代は琉球王府に文化が花開いた時期でもあり、当時盛んに行われた中国や大和(日本)、南方諸国との交易の中で様々な染色品の影響を受けながら、沖縄の気候風土にあった独自の技法を持つ紅型が誕生していったと思われます。
紅型は型紙を彫ることから染め上げるまで、すべて一人の作業で行なわれます。そのため他の型染と違い、その作風と作家個人の色彩感覚が染上がりを左右するといっても過言ではありません。
型紙の下に「ルクジュウ」と呼ばれる豆腐を干し固めた台板をあてがい、下絵に沿って小刀で突彫りします。この「突彫り」は切断面がギザギザになるため、これが紅型特有の素朴さおおらかさを醸し出す原因になっています。また紅型の模様は様々で、沖縄では見られない草花や風物なども取り入れられています。これは当時王府の直轄だった絵奉行所の絵師たちが、中国・大和の文物、風景を想いながら描いたからで、庶民の衣服だった絣織物が琉球の風物のみをモチーフとしていることを考えると、紅型がいかに特権階級の着物であったかがわかります。
糖ともち米を混ぜた糊を型紙で配置したあと、三段階に分けて色挿しをします。紅型には一般に使われる染料は使用せず、代わりに顔料と呼ばれる色科と福木、藍等の植物染料を使います。
最初の下塗りでは主に顔料を、次の上塗りでは植物染料を重ねて挿し、最後に「隈取り」と呼ばれる顔料を使った紅型独特のぼかし染めを施します。これは女性の頭髪で作った筆で模様の一部をぼかす技法で、図案全体を引き締め立体感を出す効果があります。紅型の最大の特徴は、顔料を使用している点です。顔料は染料と違い水に溶けないので、色素が生地の繊維に浸透せずその表面に着色します。そして一度着色すると永久に色が変わりません。あの、沖縄の強い日差しにも負けない鮮やかな色彩は、顔料だから表現出来たのです。
ところで、なぜ紅型は染料ではなく顔料が使われたのでしょうか。その理由は沖縄独特の気候風土にありました。四方を海に囲まれた沖縄は利水が悪く、しかもその水は石灰を多く含みます。さらに空気は塩分を含み、強い日差しは著しい退色をまねき、植物染料はなじまなかったのです。そして代わりに顔料による、沖縄独特の染織技法が生まれたのです。
北緯24度、東経122度に位置する亜熱帯の島、沖縄。中国でも日本でもない、独特の文化を築いてきた南の島の染物は、その悲観的な歴史の流れの中であまりに明るく、鮮やかです。それは沖縄王朝の末裔として今も生き続けるウチナンチュ(沖縄人)の心なのです。
牛首紬~落人伝説の織り今再び
霊峰白山の麓 石川県と福井県の県境に近く、手取川の流れる牛首谷にそって小さな集落がある。
冬には三米を越える雪に覆われる海抜2702mの山村。ここが牛首紬の故郷、白峰村である。
白峰村はその昔 牛首十八ヶ村とよばれていた。牛首村の起こりは、養老元年(07/07)に白山開闢をした秦澄大師が、この地に牛頭天皇を祀ったのが始まりとされている。牛首の由来は、この「牛頭」からきているといわれているが、定かではない。また白山一帯には落人伝説が数多く残り、この村も平氏の隠れ里だったという。そしてその落武者の妻女が村人に伝えたのが、牛首紬だといわれている。
 |
 白峰村全景 白峰村全景 |
この紬が全国に知られるのは江戸中期。大正時代には結城・大島と並び三大紬のひとつに数えられた。しかし昭和に入り戦争の勃発を境に生産数は減少、そして昭和49年、手取川のダム建設に伴い多くの牛首生産者が廃業する。このことは、牛首紬の将来を決定付けることとなった。現在僅かに2社がその生産を続けている。
牛首紬の特徴はその風合いにある。まるで結城と大島を合わせたような地厚で丈夫で、軽くて柔らかい風合いなのだ。その秘密は糸にある。牛首紬は緯糸に玉繭(蚕が2匹で作った繭)を使う。そしてこれらの繭から座繰りで糸を引く。「座繰り」とは手繰りで糸を引く。「座繰り」とは手繰るという意味で繭を鍋で煮て手で直接引くのだ。糸口が二つある玉繭は糸が絡んで機械では引けない。60~70個を煮ながら糸を引き集めた糸を勘のみで、糸の太さを一定に保ちながら一本の糸にしていく。この製法を「のべひき」といい無形文化財にされているが、今では高齢化が進み、引き手も数える程となった。引かれた糸はのべ枠に巻かれる。巻き取る動力は人力。糸はテンションがかからず。ゆっくり宙を泳ぐ。実はこの工程に牛首紬の柔らかさの秘密が隠されている。糸が空気を含むのだ。機械で引かれた糸は伸び切ってしまい空気の入る余地が無い。このような特性は、牛首紬の糸だけが持つ独特のものである。
 |
| のべひき作業 |
座繰り糸を使った紬は現在では牛首以外には無い。しかし「座繰り」という糸取りは、決して特異なものではない。古くはどの地方でも糸が取られていたのだ。それは、自分達が消費する糸である。繭の生産には、必ず売り物にならない玉繭や屑繭が出る。それを使って人々は自家用の織物を織った。座繰りは、屑繭から糸を引くために編みだされた技なのだ。そしてその自家用織物こそ、今日の紬なのである。どんなに高価なものでも紬は普段着という考え方は、ここから生まれたのだ。
耕地率が1%にも満たない牛首の人々は、生きる糧を山に託す他なかった。春の訪れと共に焼畑に山に入り、冬の雪篭りの中、糸を紡ぎ機を織る。自給自足の暮らしの中で、牛首紬が生まれたのは必然だった。この白峰村を訪れたのは、今から9年前のこと。当時はコンビニすらない山奥の閉村だった。時は移り今やIT時代。この原稿も白峰村のホームページを参照した。しかし牛首紬を取り巻く環境は、一段と厳しくなっている。作り手の高齢化、原材料不足、生産数は4000反を切っている。今回、3月の催事でも商品はともかく、実演は無理かと思った。しかし前回来場頂いた小倉きしさんに無理を願い、何とか開催の運びとなった。恐らく糸取りの実演は、今回が最後になるだろう。
何時の世でも、時の流れに文化は変質する。それは誰にも止められない。せめて時代の目撃者として最後まで見届けることが我々に出来る唯一のことなのかもしれない。「繭から糸を引き、繭が糸に生まれ変わる」きものの原点ともいえるその光景が、いつまでも続くように願って止まない。
牛首紬参考資料 //shofu.pref.ishikawa.jp/shofu/kougei2/thumugi/rekimain.htm
有松絞り~竹田庄久郎の遺産
名古屋駅から名鉄で30分、浮世絵で有名な鳴海宿の次が有松である。今から392年前、竹田庄久郎が妻、お茅と共に命を賭けて拓いた町だ。桶狭間の古戦場が近いこの辺りは、当時何もない竹林だった。彼らは鍬一本で切り開いたという。もちろん、今こうして駅から見る街並みに、そのことを伺い知ることはない。愛知県名古屋市緑区有松。有松絞り発祥の地である。
静かな町だった。駅前なのに人影が少ない。改札を出て踏切を渡る。絞りの町だけに駅前の商店はどこも絞りを店頭に使っていた。そば屋の暖簾、喫茶店のメニュー、不動産屋ののぼり、洋品店のウインドーには絞りで染めたウエディングドレスが飾ってあった。商店街を抜け藍染川を渡ると、まもなく東西に通じる旧東海道に出る。さして広くない街道の両側に古めかしい家並みが立ち並んでいた。総瓦葺の屋根、格子になまこ壁、隣屋根との境には梲(うだつ)が張り出し、江戸時代の商家の姿をそのまま現代に残している。中でも一際立派な門構え、大きな家屋敷で目を引いたのが、竹田庄久郎の血統を受け継ぐ寛保年間創業の紋問屋・笹加、竹田嘉兵衛商店だ。商家とはいえそのたたずまいは風格さえ感じる。約束の時間を5分程過ぎていた。我々は脇の通用門から中へ入ると、入り口とは思えぬほどの框の高い玄関で呼び鈴を押し、訪問を告げた。苔むす石組み、焼けたなまこ壁。鉛色の屋根の向こうに見える松の緑が鮮やかだった。間もなく引き戸は開かれた。我々は靴を脱ぐと框によじ登り、中へ入っていった。
広大な敷地だった。庭の一隅には茶室もある。建物の隅々まで贅を尽くした造りは、当時の繁栄を物語っていた。庄久郎が二代藩主徳川光友に御用商人に取り立てられ、有松絞りが藩の有力な財源になると、尾張徳川家との結びつきが強まった竹田邸は、街道を行き来する諸大名の休息場として利用された。一室に通されると座る間もなく、その人物は入ってきた。チャコールグレーのスーツ姿に口髭をたくわえ、メガネはかけていなかった。少々眉毛が垂れていたが、竹田耕三氏は写真で見るよりもずっとダンディーだった。
庄久郎の末裔である竹田氏は竹田嘉兵衛商店の専務兼デザイナー。近年、有松ではパリコレなどモード界での絞りも手がけられているが、竹田氏はその中心人物である。氏はデザインの傍ら、内外のイベント企画や講演等も数多く手掛け、97年の国際絞り会議ではパネリストも務めた。服飾の世界は言うに及ばず、歌舞伎、邦楽、芸能界などに幅広い交流を持ち、今日も本当はジュディー・オングと赤坂で5時に食事の約束があったんだが、どうしても仕事の都合で間に合わないので断ったという。ひとつひとつ言葉を選ぶ話し方が印象的だった。「あの一絞りは世界各国で自然発生的に古くから行われている模様染めでして、中央アジアのトルファンや南米ペルーなどからも15世紀前後の裂がたくさん出ましてねぇ」
しかし、日本ほど絞りに関して多様な技法が伝えられているところはないという。正倉院や法隆寺に残されている古裂の中には、現代の専門家が見ても技法を解明できないものもある。絞りは当初祭礼の垂れ飾りや調度類などの意匠に使われ、平安時代に衣服の模様付けとして利用されるようになる。やがて室町時代の「辻が花染」や安土桃山の緻密で繊細な意匠を経て、江戸時代に絞りの最高峰ともいわれる疋田絞りが登場する。絞りのシワを強調し残すようになったのは、この疋田絞りからだという。「この有松も慶長13年ですから江戸の初頭にこの町が出来て、それからすぐまあ開祖の竹田庄久郎てのが絞り始めるんですけども、まあこの東海道が江戸時代非常に盛んになるにつれ売上高生産高が上がってきまして、でそれで幕末まで繁盛するんですが幕末から下降線になるんです」明治維新による封建社会の崩壊。有松は全ての特権を無くすことになる。また鉄道の開通により街道筋の商いがさびれたことも一因だった。
「しかし明治の後期ぐらいからまた復活するんですよね。幕末から大正にかけて技術革新ここはやったんです」存亡の危機が起爆剤となり、有松では逆にこの時代様々な絞りが開発されるようになる。最盛期にはその数は百を超え、今日世界中にある絞りの種類の75%が有松でこの時期に創られた。デザインだけではない。絞り専用の生地・括り糸の研究により、従来では考えられなかった裏打ちのいらない、洗い張りの出来る生地を開発したのだ。より完成度を高め有松は復活を遂げたのである。それは、幾度もの試練と困難に遭遇しながらも有松の地を拓いたあの竹田庄久郎の初志であり、まさしく遺産であった。
紀元前のエジプトに端を発する悠久の歴史。絞りは何故絶えることなく伝承されてきたのか。「結論的には"凹凸感"だと思うのです。シワですね。布は身にまとうと必ずドレープが出来て陰影が出るんですが、絞りだとその中にさらにもう一つ陰影が出来るんです。単体でこのような表現効果を持つのは他の染織法では無いんです」今日有松絞りの技術は服飾の分野に止まらず、スピーカーボックスの音響効果など工業分野まで応用されている。その有松が今一番憂慮しているのが後継者問題である。有松は昔から集落単位で異なる絞りを生産してきた。その地域の中で親から子へと技術は継承された。
「例えば三浦絞りをやってる中で稼ぐと一生三浦なんですが、違う括りをやってる部落へ嫁ぐと、娘のときに三浦やってて嫁いでから手蜘蛛なら手蜘蛛絞りって二種類やるんです。しかし…」括りの技法を習う家庭環境が失われつつある今日、"一人一芸"と呼ばれる高度な技術を守っていく事は難しい。「将来的には確実に無くなります。ですから僕は今どんどん欧米に技術を"輸出"してるんです。今まで産地は技術をオープンにするのを拒んできましたが、僕に言わせればそんな時代はとっくに過ぎてるんです。底辺を広げる努力をしなければ本当に滅びてしまいますよ」いつかメイド・インUSAの有松絞りが出来るのかもしれない。厳しいがこれが現実なのだ。時間はとうに過ぎていた。我々は時間を割いて頂いた竹田氏に深謝し、絞り会館へ向かうべく竹田嘉兵衛商店をあとにした。
絞り会館では絞りの実演を行っている。絞りの技法は糸だけで括るもの、縫い締めるもの、布を細くたたんで絞るものなど、大別すると8つに分けられる。今日の実演は三浦絞りと縫い絞りだった。一人の女性は六十代、もう一人は八十を過ぎてるだろうか。括り台に向かい黙々と括っていった。印をのところを鉤針に引っ掛けて粒を作り、器用に糸で括っていく。丸い小さな背が、有松の歴史を物語るようだった。「このおばあちゃんはもう七十年も括ってるんです」「きゃっはっはは歳がバレるでにゃーか」彼女らは年端もゆかない頃から括りを覚え、括ることにその人生を費やしていた。ただ括るのみ。己の括ったものがどの様な柄になるのかさえ、彼女らは知らないのだ。「そーんなこたーにゃーよ、今はしぃーとるわい」
とにかく、このような括り人によって有松絞りは支えられてきた。いくら元気でも歳は歳である。彼女らの健康を願い、そして彼女たちの目がいつまでも青くならないことを祈った。
名古屋駅は夕方のラッシュで混んでいた。名物の味噌煮込みうどんを食べたかったが、新幹線の時間まで15分しかなかったので、諦めてビールを買った。後で聞いた話だが、あの金さん銀さんも括りをしていたという。やっぱり指先使ってるから、いつまでも元気でボケないんだろうな。帰ったら教えてやろう。「やっぱり止めとこ…」今更金さん銀さんになってもらっても困る。人生は全てザッツ・ライトなのだ。電車が入ってきた。我々はバッグを持つとホームへ向かった。
子供の成長祝い・七五三
七五三は、毎年11月15日に三歳、五歳、七歳に達した子供に晴着を着せ、その成長息災を神社に祈願する行事で、子供の通過儀礼の代表的なものです。七五三は祝いは今日でも全国的に見られる風習ですが、子供の誕生や成長を祝う行事はかなり古くから行われており、平安時代にはすでに記録として残されています。
成長祝いの行事のほとんどは神や仏の加護を願い求めるために生まれ行われてきました。現代とは違い、社会基盤や生活環境が整っていなかった古の時代は、子供の無事な成長をただ祈るしかなかったのです。乳幼児の死亡率の高いこの時代は、子供の健やかな成長の節目を祝う事は、現在とは比較にならないほど大きな意味を持っていたようです。
七五三という奇数を重ねた呼び方が使われるのは江戸時代の頃からで、庶民の間で一般的に行われるようになったのは明治以降です。なぜ七歳、五歳、三歳かというと、これは平安時代に行われていた子供の成長祝いの儀式の年齢に端を発しています。しかし根本には、やはりその年齢の死亡率の高さからあったのではないかと思われます。
三歳児の生い立ちの原型は、平安時代から行われていた「髪置き(かみおき)」または「髪立ち(かみだち)」と呼ばれるものです。当時の乳児は胎髪を剃り、三歳になるまでは頭上に丸く髪を残す芥坊主などの髪型でした。その髪を伸ばし始める儀式でしたから、男女ともに行われていました。また不安定だった乳児が、三歳まで無事に育った事を祝う意味もあったようです。
五歳の祝いの原型は、平安時代の公家階級で行なわれていた初めて袴をつける「絝着」の祝いです。この元になるのが、さらに古くから行われていた「着絝の儀」で、基盤の上に立たせた男児を吉方に向かわせ、袴を左、右と踏み込ませて着せる風習でした。
ところで、なぜ11月15日が七五三なのか、実はこれはいまだよく分かっておりません。陰陽道でいうところの吉方であるという説、収穫祭としての氏神祭に当たる日に固定したという説、農耕中心だった時代の名残で、その日あたりがちょうど収穫が終わって一息ついたところだったという説や、または天和元年、将軍・徳川綱吉の子、徳松の祝儀を11月15日に行ったところから、一般にこれに習うようになったという説など諸説さまざまなのですが、今日では特別この日にこだわらず、11月初めから中頃までの間でそれぞれの都合に合わせて行われるのが一般的なようです。
ご存知ですか?十三参り
先日ある方から「十三参りをしたいのだが、この辺ではどの寺に行ったらよいのか」と聞かれました。関西では一般的のようですが、こちらではあまりなじみがなく、「へえ、十三参りですか…?」と返答に困ってしましました。十三参りとはどういうものか、何処へお参りに行ったらいいのか、関東の方のために(関西の方も)調べてみました。
十三参りは関西ではなじみ深い行事で、十三歳の男女が虚空蔵菩薩にお参りし、厄難を祓い知恵を授けてもらうように祈願する行事です。虚空蔵菩薩とは、宇宙大の森羅万象をことごとく抱擁する蔵になぞらえ、生き物全てを守護し、祈願する者の業を清め知恵を授けるものといわれ、十三歳という本来なら男子は元服、女子は少女から大人へと肉体的、精神的に大きく変化していく時期を区切る意味で、十八世紀後半から始まったと伝えられます。この十三参りで有名なのが京都嵐山の法輪寺。京都で十三参りといえばこの法輪寺のことで、本尊の虚空蔵菩薩は「嵯峨の虚空蔵さん」と呼ばれ親しまれています。毎年四月十三日になると、数えで十三歳になる子供達がお参りするのですが、京都ではすでに江戸時代中頃には、春の行事として法輪寺に参拝することが一般的だったようで、「難波より 十三まゐり 十三里 もらひにのほる 知恵もさまざま」という歌でわかるように、当時は京都のみならず近畿一円からも参拝する人々が多かったようです。法輪寺は洛西の嵐山にあります。途中桂川に架かる渡月橋を渡っていくのですが、この渡月橋は別名「法輪寺橋」ともよばれ、法輪寺の参拝のために作られました。法輪寺の位置は御所から見て西になり、これは末法思想でいう「浄土」にあたり、桂川を挟んで日常と浄土というように考えられています。
法輪寺での参拝は、写経と同じ意味で色紙に自分の好きな一文字を一時書いて納め、本堂で祈願してもらいお守り袋をいただきます。帰りはまるた150メートルほどの渡月橋を渡るのですが、この時渡り終えるまで後ろを振り向いてはいけないと言われています。振り向くと、せっかく虚空蔵菩薩に授かった知恵が消えてしまうという言い伝えがあるのだそうです。また、京都以外の他の地域でも、虚空蔵菩薩を奉っているところではこの風習が見られ、虚空蔵菩薩を奉った寺社も全国各地に散在しています。
十三参りは、虚空蔵菩薩を奉っている寺社にお参りするのが一般的ですが、形式にとらわれず、人生の一つの区切りとして親子でお参りするのであれば、他の寺社でもよいのかもしれません。なお、神奈川・東京にも虚空蔵菩薩を奉った寺社がありますので、いくつか列記しておきます。
東京都内: 大空閣寺 世田谷区瀬田町4の21の15
勝光院 世田谷区桜1の26の35
神奈川県: 正覚寺 横浜市港北区茅ヶ崎町782
雲松院 横浜市港北区小机町1451
天応院 相模原市下溝780
ゆかた今昔~ゆかたのルーツのお話
ゆかたは、もとは湯帷子(ゆかたびら)といい、平安時代以来、上層階級の人々が、入浴の際や湯上りに着た麻衣の事でした。当時の風呂は、今日のような浴槽のものではなく、サウナのようないわゆる蒸風呂で、高温の蒸気から肌を守るためまたは宗教的意味合いから、麻の単衣のきもの(帷子)を着て入ったのです。のちにきものを脱いで入浴するようになると、この湯帷子は風呂上りの湯気を吸い取るものとして使われました。同時に、ゆかたびらの「びら」を取って「ゆかた」というようになり、布地も水気も吸いやすいもので、広袖の単衣のものに変わりました。それがやがて入浴後だけでなく、夏に着る衣服の意に転じていったのです。
民間でゆかたを着るようになったのは、江戸時代の初めのころで、木綿地の普及とともに、麻よりも染まりのよい木綿のゆかたがさかんに用いられ、江戸中期の浮世絵には、ゆかた姿が多数多く描かれており、もっぱら花柳界の女性や町人が着ていました。西鶴の「好色一代女」には、「黄枯茶に刻み稲妻の中形、身せばに仕立て」とあり、当時から中形染(小紋などに対し、中くらいの大きさの柄)が行われていたことがわかります。
18世紀後半になると、ちりめん地のものや絞り染、小紋柄など、ゆかたの種類も多くなり、明治以降は幅広い階層にわたり、買い物や気軽な訪問の際にも用いられるようになりました。明治31年の「都の花」には、「中世の出世」と題して、ゆかたがゆかたの域を脱して流行していたことが記されています。
そのゆかたが、今日はまたブームになっています。特にここ数年、若い人の間では夏ならではのファッションアイテムとして大人気で、花火大会や縁日はゆかた姿でいっぱいです。というよりも「花火見物や縁日用のコスチューム」といった感じでゆかたを捉えているのが特徴です。色もカラフル、柄も豊富で、花、動物、抽象柄、風景、のりもの、爬虫類など、ありとあらゆるものがモチーフされ、むしろ紺白ののものを探す方が難しいほどです。いかに日本の夏をオシャレにキメるか、そのための必須アイテムの最たるものなのです。
もちろん、ゆかたは間違いなくきものです。季節感をもっとも表わす、日本の伝統的な和服です。と同時に、「あれってさあ、花火大会とかに着るやつじゃん」でもあるのです。
どうか皆様も、今年の夏は是非とも、日本のこの"伝統的な和服"でカッコよくキメていただきたいと思います。
ご存知でしたか?お正月のしきたり
言われてみれば知らなかった「お正月」のあれこれ。今回はお正月の「素朴な疑問」の巻です。
■その1:なぜ1月を「正月」というの?
「正」は「ただしくする、きちんとする、ちょうど」などの意味があり、「あらたまの年のはじめ」というように、一年のはじめの月の意味があります。昭和20年頃までは日本人が歳をとるのは誕生日ではなく、元日でした。家中みんなが一緒に年をとって正月を祝いました。そのため、正月にはご先祖様であり農耕神でもある「年神さま」を迎えて、様々な行事で新しい年をお祈りしたのです。ご先祖様が春には田の神になり、秋には山の神になり、正月には年神さまとなって子孫の繁栄を見守ってくれると考えられていたわけです。
■その2:「元日」と「元旦」は違うの?
「元」は物事の始まりのことで、「元日」は年と月と日の3つの始まりを表わしています。「元旦」は一年の初めの旦(あさ)の事で、1月1日の朝をいいます。元旦の明け方、一家の主またはその年の年男は、家の四方の神社に向かって拝して、若水を汲み、神棚、仏さまに備え、雑煮の湯を沸かすことが"元旦の仕事始め"とされていました。「明けましておめでとうございます」とは、新しい年神さまをお迎えして、その神さまをたたえる言葉なのです。
■その3:鏡餅にはどんな意味があるの?
鏡餅は、神さまのお供え物であり、元日に新しい年の神さまが宿るご神体でもありました。ですから本来は神聖なもので、その意味でいえば"サトウの切り餅"とはいかないようです。供え方は一般的には三方に奉書を敷き、昆布をたらし、裏白を置きその上に二つ重ねの鏡餅をのせますが、縁起物ゆえそのカタチは地方によって様々です。鏡餅は正月11日に下げて、雑煮やお汁粉にして食べます。これが「鏡開き」で、本来は刃物を使わず、手などで割り開いて食べるものでした。
■その4:お屠蘇・お雑煮の意味は?
お屠蘇は、本来は薬草を酒に浸した薬酒でした。お屠蘇には体内の邪気を払い、長寿になる薬効があるといわれ、中国から伝来した風習です。お雑煮は、年神さまにお供えしたもの(お餅やダイコン、にんじんなどの野菜)を、神さまと共にいただく食べ物です。お供えした食べ物には神さまが宿り、食べることによってその力を身に付けることが出来ると考えられていたのです。
■その5:門松・注連飾は何を意味するの?
門松は正月の年神さまを迎え、お祭りする場所を示すもので、いわば目印といえます。古くから松に限らず常緑樹を飾ったといわれ、松を立てるようになったのは平安後期から、竹を添えるのは鎌倉時代以降といわれています。注連縄は、神事のときに神聖な場所と俗世間とを区切るために用いられるもので、「標縄」と書いたり、三筋、五筋、七筋のわらを下げることから「七五三(しめな)縄」と書いたりします。昔は祭られる場所全体に張り巡らしたのですが、次第に簡略化され、現代のようなお飾りになりました。
■その6:お正月はなぜお年玉が出るの?
お年玉の始まりは、神前に供えた丸餅でした。年神さまの魂のこもった餅を「年玉」と呼んで人々に分配したのです。江戸時代に入って、商家の主人が奉公人に餅の代わりに金銭を与えたことが、今のお年玉の形になりました。神さまの力を分け与え、今年もガンバレと、励ます意味が込められているのです。
節分考察~あなたの知らない節分のお話
二月三日は節分です。節分というとすぐ「豆まき」を連想しますが、何故「豆まき」なのかご存知ですか。元々節分とは暦のうえでの立春・立夏・立冬の「前日の日」のことで、年に4回あるのですが、中でも立春が一年の初めで最も重視されていることから、一般に「節分」といえば春の年の邪気を祓う「追儺(ついな)」と呼ばれる行事が行われます。その代表が「豆まき」なのです。
節分という概念は古代中国の思想「陰陽五行説」から来ています。これは、この世は全て「陰」と「陽」(善と悪、光と影など)に分けられ、さらに「木火土金水」の五気の作用(五行)によって森羅万象が創られるというものです。平安時代になると、この考え方はあらゆる基本となり、節分も四季をこの考え方に当てはめ、一月から三月までを春として、立春を一月、春分を二月としました。当時は太陽太陰暦で立春が年初でした。つまり旧暦の一月一日元旦は、今の新暦二月四日なので、前日の二月三日が節分になる訳です。ところでなぜ節分に邪気をはらう必要があったのか。これは陰陽五行特有の方位「鬼門」が関係しているのです。
当時の数を数える単位は「子・丑・寅」の十二支でした。一年も十二支に分け、一日も「子の刻、丑の刻」と十二支で言い表しました。この関係を方位で表すと北が「子」で十一月になり、時計回りに方角、十二支、月、時間が全て表せます。すると節分の二月三日は旧暦の十二月三十一日になり、方角が北東で「丑」となります。実はこの北東の「丑寅」の方位が鬼・邪気が出入りするという「鬼門」の方角にあたるのです。そのため新年を迎えるには、邪気をはらう追儺の儀式が必要だったのです。
では何故「豆まき」なのか。そこには前述の「五行」の作用が絡んできます。「五行」とは「木火土金水」の五気の作用をいいます。これらは互いに生かしたり(相生・そうじょう)殺したり(相剋・そうかつ)する関係を持ち、例えば「金気」は「木気」を剋する「金剋木」の関係にあります。節分は迎春の儀式ですが、春は「五行」ではこの木気にあたり、その木気が苦手とするのは「金剋木」の関係にあたる金気です。そこで金気を封じるため、今度は「火剋金」の関係から火気の性質のものを求めたのです。金気は硬いものを意味し、豆がこれに相当します。その豆を火で煎る行為は「火剋金」であり、煎られた豆を投げつけ、痛めつけることで金気を封じる、つまり鬼門封じになるわけです。北東の方角を「鬼門」としたのは、古代中国の道教「泰山冥府信仰」からきており、その泰山という山が北東に位置したことから冥府=北東=丑寅=死となったとされています。「草木も眠る丑満時」や「丑の刻参り」という言葉も、時間の方位が鬼門に向いているからであり、鬼が牛の角を付け寅皮のパンツをはく理由も、この「丑寅」からきているようです。ところで豆まきの時には「鬼は外、福は内」という向上がつきものですが、鬼にもいろいろ居る(?)ようで、地方によっては必ずしも鬼は「外」ではないようです。そこで最後に全国の鬼の"処遇"のいくつかをご紹介します。
【新宿歌舞伎町の鬼王神社】…鬼が御祭神なので「鬼は内、福は内」。
【入谷の鬼子母神】…「福は内、悪魔外」。
【愛知県の大須観音】…「福は内」だけ。鬼の面が寺宝なので「鬼は外」は唱えない。
【福島県の二本松地方】…「鬼外」と「ワ」を抜かす。二本松藩の殿様が丹波氏なので「鬼は外だと」「お丹波様外」になってしまう。
【埼玉県武蔵嵐山の鬼鎮神社】…鬼門を守るために作られた神社で、鬼が豆をまいて厄払いをしてくれる。口上は「鬼は内、福も内、悪魔外」。
【群馬県鬼石町】…「福は内、鬼は内」。鬼が作った町といわれ、鬼が守り神。近年では、全国から追い出された鬼の安住の地となっている。
お節句のお話
風薫る五月。五月は若葉の緑が目にも鮮やかな月でもあります。その新緑によくマッチするのが、青空に泳ぐ錦の鯉のぼり。そして鯉のぼりといえば、そう、端午の節句です。相変わらず強引なオープニングではありますが、今回は「お節句」についてです。
「はしらのきずはおととしの~」と唄われるように、五月五日は端午の節句。なにが節句というと子供のお祝いのようにとらえがちですが、もともとは古代中国の易学から来ている考え方なのです。これは陰陽五行説といって一切の万物は相反する性質を持つ陰・陽二種の気によって生じ、全ての事象はこの二気の消長によって説明されるというもので、節句はその暦の上の忌みで禊ぎをして邪気を祓う「しきたり」でした。
節句には五月の端午の節句、三月の桃の節句以外にも、一月七日の七草の節句、七月七日の七夕の節句、九月九日の菊の節句と五節句あり、すべて奇数月です。これは奇数を陽の数、偶数を陰の数とし奇数を重んじたためです。日本でこの五節句が定着したのは江戸時代で、今日でも節句のならわしとして受け継がれています。
■七草の節句(人日)一月七日
「せり なずな ごぎょう はこべら ほとけのざ すすな すずしろ これぞななくさ」春の七草をうたった歌ですが、どれがどれだか残念ながら分かりません。それはともかく、七草粥を作り、冬場に少しでもビタミンを補い疲れた胃を休めることは、長い経験の中から積み重ねられた先人の知恵です。
■桃の節句(上巳)三月三日
古来中国から伝わった三月の初めの巳(み)の日という意味で、正式には上巳(じょうし)の節句といいます。平安時代の御人形(ひいな)遊びと、紙やワラで作った簡素な人形(ひとがた)に、自分の厄を移して海や川へ流した流し雛の行事が結びついたのが、現在のひな祭りです。雛人形を飾ることは、健康で優しい女の子に育つように、厄を除け、幸せになりますようにとの家族の温い思いが込められているのです。
■端午の節句(菖蒲)五月五日
端午の節句は古来、邪気を祓うため菖蒲を軒に挿した事から菖蒲の節句といわれ、その音に通じるところから尚武の節句ともいい、そこから男子の節句とされました。ちまきや柏餅を食べ、鯉のぼりや鎧兜などの五月人形を飾り子供の成長を祝うのですが、鯉のぼりは「外飾り」といって立身出世、鎧兜、武者人形などは「内飾り」で厄除け、身体健勝と、それぞれ飾る意味が違うそうです。
■七夕の節句(星祭)七月七日
宮中の祭りで、女性の裁縫の上達を願って行われた祭りでしたが、後に諸々の技芸の上達を願うものになりました。農耕的行事としても豊作祈願や雨乞いなど、厄払いとして盛んに行われました。織姫と彦星の天女伝説はポピュラーですが、元々は地に足が着いたお祭りなのです。
■菊の節句(重陽)九月九日
古来中国では九は陽数の極とされ、九が重なるこの日は大変めでたい日とされていました。日本でも過去には菊花の宴として、菊の花を浮かべたお酒を飲む風習がありましたが、今日では菊の品評会などがその名残りとして残っているだけです。
きものの歴史(1)~きものの生い立ち
日本のきものの原型は小袖といわれています。その昔、中国の影響を大きく受けていた日本が独自の道を歩み始めたとき、この世界に類を見ない美しいきものの祖先が生まれたのです。
■弥生・古墳時代
弥生時代の日本人の服装は、紀元前はもとより紀元2~3世紀頃のものも埴輪などから推定するしかありません。それによると上衣は男女とも前合わせの短い上衣で、下は男子は褌(はかま)と呼ぶズボン形式の、膝下を紐で結えたものをはき、女子は丈の長い腰巻き風の裳(も)を用いていました。もっとも埴輪に残るくらいですから、これは相当身分の高い人たちの服装で、一般庶民に関しては「魏志倭人伝」という文献に、貫頭衣という頭からすっぽりかぶる、原始的な衣服を古代日本人は着用していたと書かれています。これはいわゆるポンチョに似たもので、言うなれば、ゲゲゲの鬼太郎のねずみ男の様な恰好と推測されます。
■飛鳥・奈良時代
6世紀後半になると中国との交流が盛んになり、国家体制や文化水準も次第に中国式になっていったのですが、その大きな変化となったのが、7世紀初めの律令制度の導入による衣服に対する格付けでした。すなわち、衣服を天皇家を中心として礼服(公家)、朝服(朝臣)、制服(一般役人)の三種類に分け、これらの服装を着用する事により身分の区別をしたのです。代表的な男子の朝服は冠に長い袍(ほう)と絝をはき、腰に革帯を締めて、袍のの色の違いによって官位を表わしていました。一方、女子は裙(も)と呼ぶ上衣に紕帯し、その上に袖なしの背子(はいし)という短衣とスカーフのような長い比礼(ひれ)を肩から掛けていました。
このように当時の日本は、中国の時代文化をそのまま模倣したような国づくりだったのですが、その後の国際情勢の変化によって独自の文化を育んでゆくことになるのです。
きものの歴史(2)~小袖誕生
■平安時代・大陸からの独立
七世紀の終わりに桓武天皇が京都に都を移し、平安時代を迎えます。当時の日本は中国などの大陸文化の模倣で、公家・貴族を中心とした荘園政治が行われていました。これらの時代は儀式も立礼が主であったため、服装もそれなりに便利な二部式が着用されました。しかし唐との文化交流が遣唐使の廃止や、その後の唐の滅亡のよって途絶えるに従い、逆に日本的な文化が開化し始めていきます。そしてそれに大きな役割を果たしたのが、公家・貴族に変わって力をつけてきた武家の台頭でした。
公家・貴族の中国一辺倒の感覚に対し、各地域で勢力をつけてきた豪族である武家は、より日本的な伝統的生活様式を求め、その流れは立礼の習慣を次第に座式の生活様式へと変化させ、それにともなう衣服も変わっていきました。これが平安時代の後期に見られる朝服が変化した束帯や、さらに簡略した直衣、さらに仮衣として一般化した制服で、これらは細部においても袖を広くして着やすくするなど、日本的生活様式にマッチするよう改良されていました。
一方、女子の衣服もこの時代を象徴するものに十二単衣があります。実はこの十二単衣という呼び方は後世になって呼ばれた重ね着の名称で、十二枚着るから十二単衣というわけではなく、特別枚数には関係がないそうです。むしろ色重ねの調和美からくる豪華さと貴族的誇示に意味合いがあったと言われています。皇太子殿下と雅子様のご成婚に際して行われる「決婚の儀」では、それぞれこの束帯と十二単衣をお召しになるわけですが、こう考えると今まで知識の一片でしかなかった平安絵巻が、ちょっと身近なものに感じられるかもしれません。
■和服原型の開化
これらの衣服が更に省略、簡略化して、肌着として着ていた小袖が中衣化し、さらに上着へと発展していきます。きものの原型である小袖の登場です。ところで中国の影響による立礼服から小袖に至るまでの変化で興味深いのは、それが常に簡略化、省略化を辿っていることです。そしてさらに衣服の簡略化の帰結である小袖が、上着ではなく肌着だったということです。もちろん、服装が庶民に浸透する過程で、過飾の部分が省かれていくのは当然なのですが、この小袖の登場は、あたかも一枚づつ上着を脱いでいった結果小袖にたどり着いた、という印象を受けるのです。実はこの固有の民族衣装である小袖が生まれるまでの背景には、日本特有の風土が大きく関わっていたのです。
日本の気候は大陸とは違い、四季がはっきりして寒暖の差や湿度の変化が大きく、しかもそれが微妙に絡み合いながら移ろいでいきます。人々は日々の暮らしの中で、その時その時の、微妙に変化する気候風土にあった衣服を、文字通り肌で感じて形作っていったのです。たとえば十二単衣は当初「襲」であったわけですが、後に唐衣や裳を省略して、表着の上に小袿(こうちき)だけとする小袿姿、表着も打衣も省略した袿と小袖、または絝の袿姿、さらに小袖と絝だけの姿などと、その四季折々の気候に応じて衣服を組み合わせたのです。
日本の風土に培われた小袖-遣唐使廃止から実に200年目にして、ようやく日本人が手に入れたアイディンティティーでした。
きものの歴史(3)~鎌倉・室町時代のきもの
栄華の限りを尽くした公家・貴族の支配に幕を閉じ、院政に続く武士階級の台頭で十二世紀に入り、鎌倉時代を迎えます。この頃の服装は平安時代の流れを簡略する一方で、公家や武士の衣服が庶民に、庶民の衣服が武士階級へと交流を深め、女子の服装は襲(かさね)が分解され、袴がはずされていきました。小袖衣裳の定着です。藍染や草木染などの染色技術の普及による文様の発達が、下着として用いられていた白の小袖を表の小袖に独立させ、筒袖も幅広の袖へ変化していきました。
さらに十四世紀になり室町時代に入ると、服装を含めた大きな風俗変化が起こります。その背景になったのが、1467年の応仁の乱をスタートとした戦国時代の幕開けでした。
足利将軍家管領の相続問題をきっかけとして細川勝元が起こした大乱は、京の都を戦乱の巷に落とし入れました。弱肉強食の世は貧困を極め、食べるだけで精一杯になり、身分階級の差別が服装の面ではなくなったのです。しかし、新しい服飾が生まれなかったかわりに小袖がそうであったように、これまでの服装を応用して着用しようとする生活の知恵が生まれたのです。そして出来たのが道中の塵除け防寒着としての道服や、出陣用に着た陣羽織、女子の外出着としての壺装束などです。
一方で、服装が簡略、省略なので庶民の中にどんどん溶け込んでいったのですが、戦乱の時代の心の荒みを癒すために茶の湯、能の行事が興ってきたのもこの時代です。今日、精神文化の原点とされ、もっとも日本的な支えとなっているこれらの行事が、太平の世ではなく、乱世の流れの中で芽生えていったことに、その民族的なマインド・ルーツを汲みとることができます。
きものの歴史(4)~安土・桃山時代のきもの
足利幕府崩壊で天下を取った織田信長から豊臣秀吉を経て、徳川家康に至る安土・桃山時代はわずか三十年の期間でしたが、群雄割拠の武将を統一し再び平和が取り戻され、しかも戦乱の反動と経済の復興とが相乗的に作用して、世相は活気にあふれていました。商業が活発になり、都市を中心とする町人文化が勢いを増してくると、ふたたび服飾の華美化が起こってきます。それが染色技術の向上を促進して、後世に特筆される、もっとも豪華な安土・桃山文化を生み出しました。現代のきものに施される染色技法の多くは、実はこの時代に作られたものです。戦乱で抑圧されていた感性が一度に芽吹いたわけです。
この時代の服装は、いうまでもなく小袖が中心的な役割を果たしていました。この頃の小袖は、もうすでに大袖の下に着る下着を称して言われていた素朴なものとは違い、優れた染色加工技術の導入で、豪華な外出着としても"きもの"になっていました。当時の小袖のディティールは身幅が広く、袖幅が狭く、衿下は短く衿が長い。袿幅は広く、裄丈は短く袖口は小さく、丈は対丈でした。
模様は多彩で、その表現技術は摺箔と刺繍、絞りを多く用いていました。刺繍に金・銀の箔を併用した豪華な繍箔は、桃山時代の代表的な染色技法で、幻の染といわれている「辻ヶ花染」も、この時代に生まれました。
庶民の小袖はそれでも働くのに都合の良い筒袖であったし、対丈の長着に細帯、腰に三幅前垂れのような布を巻いて日常着としていましたが、このような小袖姿の色彩的な華やかさや、ますます自由な軽快さは、当時の人々の心情を表わしていたのかもしれません。
きものの歴史(5)~江戸時代・その1
三百年間の太平が続いた江戸時代は、一方で外国文化の流入を防ぐ鎖国政策を進め、他方で封建制度の上で士農工商の身分階級を厳しく確立していったのですが、経済力を握ったのはしかし商人であり、商家が逆に力を付け、その富裕化が目立ちました。もちろん服装にも影響は及び、それは文様(意匠付け)の変化という形で表れました。
それを小袖に見ると(安土・桃山時代から)江戸初期にかけての全体に施された細かい縫箔(桃山様式)の、いわゆる慶長文様に代わって、大きな柄付けの、しかも簡略化された意匠付けが流行してきました。それが江戸中期にかけての寛文文様、元禄文様と呼ばれるもので、裾模様、肩裾模様(上半身と裾だけの構成)、肩身替模様(背を中心とした左右の違い配色模様)、上方展開模様(裾から肩へかけて配した模様)など文様を大胆に展開する技法が用いられました。特に元禄時代(17世紀~18世紀)には、それまで単なる紐に過ぎなかった帯が、ようやく帯としての形式を整えるにしたがって、小袖模様が腰を境に上下に構成されたり(割文様)、褄下から裾にかけてのみの文様配置(褄文様)など、帯の存在を前提とした文様が次々に作られました。また袖模様を表地だけでなく、袿や裾など、表から見えない所に文様を施す裏文様も現われ、すでにこの頃から粋や洒落といった江戸情緒が芽生えていたことがわかります。そしてもうひとつ、きものの染の代名詞である友禅染が、宮崎友禅斎によって生み出されたのもこの時代です。京都の智恩院の門前で、扇子に肉筆画を書いて生活していた一介の絵法師が描き出した華やかな絵模様は、のちのきものの染色技法に、ひとつの方向性を示したものとして、今日に至っています。
7世紀の律令制度の導入から始まった日本のきものの変革は、千年以上の月日の流れを経た江戸時代になり、ようやく現代のきもの姿といえる形になったのです。
きものの歴史(5)~江戸時代・その2
■慶長文様
関ヶ原の合戦で、徳川家康が勝利を占め、江戸幕府を開くまでの20年間の時代を慶長といい、この時代の特色ある一様式を慶長文様、または慶長小袖といいます。この桃山時代と江戸時代前期は、互いに隣接しているのにもかかわらず、その文様は形状、意匠などの点で対象的といえるほどの違いを見せています。
慶長文様の特徴は、そのほとんどが黒、紅、白の3色を主体として染め分け、桃山様式に見られるような華麗な色彩構成が無いことです。文様表現でも桃山様式では刺繍が主役でしたが、慶長小袖においてはどれが主役ということもなく、繡、箔、絞りが均等に扱われています。また全体に摺り箔の小さな柄を置いたものは地なし小袖とよばれ、慶長文様の一典型です。生地は桃山期の無地の平絹から、地紋のある綸子が使われるようになり、小袖の形態も桃山時代の、身幅の広く袖幅の狭いものから、身幅と袖幅がほぼ同寸の、より現代のきものに近いものになっています。
黄、浅葱、紫といった明るく華やかな趣から、黒、白、くすんだ紅などの重く沈んだ色調に。伸びやかで力強く均整のとれた区画構成は、小さく繊細で、直線と曲線が交差した複雑で抽象的な意匠構成へ。豪壮華麗な秀吉の気風に比べ、家康は質実で質素を旨としていたといわれます。時代を接してなお対照的だった桃山と慶長の文様。陽から陰へともいえるその変貌は、豊臣から徳川へと大きく流れて行った、時の権力の移行と軌を一つにするものなのかもしれません。
きものの歴史(5)~江戸時代・その3
■寛文模様
寛文模様の特徴は余白を無くしてしまう慶長模様とは違い、余白(無地場)を模様と対比させて表現している点です。柄は一般に肩と裾にポイントを置き、右肩または左肩から前裾にかけて大きなカーブを描き、大胆で動きのある意匠が用いられます。模様は多彩で動物的だけでなく、器物や文字など幅広くモチーフとされ、特に具体的な形態と文字を組み合わせて、例えば網の上に「鳥」の文字を配した模様を、「霞網に掛かった鳥」と暗示的に表すといった、ひとつの主題を機知的に表現する模様構成などは、寛文模様独特のものといえます。
このように慶長模様とは180度違う寛文の意匠は、それゆえこの時代になって突然生じたわけではないようです。慶長小袖が文献などから主に上層武家階級を対象として制作されたと推定されるので、これとは別に町人的な嗜好を反映した小袖の系統も存在したはずです。つまり慶長模様と寛文模様は、その発達が同時進行だったと考えられるのです。実際にそのどちらとも言い切れない意匠構成の小袖が、同じ江戸時代の初期に存在しています。寛文頃には小袖が既に一般の人々にも身近なものとなっていました。進取の気に富む町人階級はかぶき者は遊女の風俗を介して、次第に表出性の強い小袖意匠を生み出して行き、ついには寛文模様という様式の完成に至ったのです。
ところでこの寛文模様の発達は、とりもなおさず町人階級の台頭を意味しています。そのきっかけとなったのが、実は明暦3年(1657年) に起こった明暦の大火、俗に言う振袖火事なのです。死者10万人を出し、市中を焼き尽くしたうえ、江戸城本丸をも焼いたという大火事は、その復興を担った町人階級の経済力を飛躍的に上昇させ、町人の嗜好を多分に含んだ寛文模様という意匠を作り出す原動力となったのです。
きものの歴史(5)~江戸時代・その4
■振り袖火事~振り袖に乗り移った恋の炎
承応3年(1654年)麻布百姓町の質屋、遠州屋彦左衛門に梅野という16歳の一人娘がいた。ある日この梅野が母親と本郷丸山の本妙寺に墓参りに出掛けた道がすら、振り袖姿の一人の小姓に出会った。見れば水もしたたるほどの美少年。一目惚れした梅野はどうしても忘れられず、せめて振り袖だけでもと少年と同じ振り袖を母親に作ってもらった。しかし想いはますます募り、恋やつれした梅野は美少年を探し出せぬまま、ついには翌年17歳で死んでしまう。父親は供養のためと、遺品となった振り袖を本妙寺に納めた。ところが寺の住職はこの振り袖を古着屋へ売ってしまったのである。翌年、梅野の一周忌に本妙寺に行った彦左衛門は、病気で17歳で死んだという娘の葬儀に出くわした。棺を見るとその上には梅野のものと同じ振り袖がかぶせてある。さらにその翌年、彦左衛門が梅野の三回忌に本妙寺へ行くと、またも17歳の病死の娘の葬儀に出くわした。棺を見るとその上には同じ振り袖がかけてある。あまりの奇縁にわけを聞くと、亡くなった娘は町の古着屋からその振り袖を買ったが、ほどなく病気になって死んだという。そこへ前年に亡くなった娘の父親も一周忌でやってきて、見覚えのある振り袖に驚愕した。三人の父親はこの振り袖を寺の庭火で焼いてもらうことに決めた。元はといえば自分が古着屋に売ったことから始まったこの振り袖の不吉な因縁に、住職もさすがにおののき、振り袖供養を引き受けたのである。
明暦3年(1657年)1月18日。この日は朝から強い風が吹いていた。前評判を聞きつけて来た群衆の前で、住職はやむなく振り袖に火をつけた。と、その瞬間烈風が吹き寄せ、あっという間に振り袖は舞い上がっていった。風に乗り、本堂の上に飛んで行き、まず本堂に火が移る。火は風を呼び、風は火を呼ぶ。烈風にあおられた炎は更に勢いを増し、炎の帯は湯島から八丁堀、深川へとまたたく間に広がっていった。翌日には江戸城天守閣を焼き落とし、ついには札の辻の海岸まで焼き尽くしていった。
娘の恋の炎は狂気の紅蓮の炎となって、江戸中を飲み込んでいったのである。
きものの歴史(5)~江戸時代・その5
■元禄模様
元禄という時代は、江戸時代中期の1688年から1703年までの将軍綱吉の時代を差しますが、世に言う元禄時代とはもっと幅を広げ、17世紀中頃から18世紀にかけて町人文化が興隆し、江戸の文化が頂点に達した時代をひっくるめた名称といえます。
そのため、元禄風といえばきものだけではなく、元禄時代の派手な生活風習一般を差し、たとえば当時大流行した歌舞伎の上方役者、佐野川市松の衣装で知られる市松模様も、ひとくちに元禄模様と呼ばれています。
しかしこの時代を代表する大きな意匠形式の変化は、模様染の出現でした。模様染とはその名の通り染めだけで模様を表現したものですが、そのきっかけとなったのが、天和3年に出された総鹿子および金銀繍入り衣類の禁止令でした。風俗の引き締めを目的としたものでしたが、慶長、寛文を通して常に権力階級から生み出されてきた絞りや繍箔などの染織技法が、この時代になって奇しくも公儀から禁止されたのですから、いかに町人文化が爛熟していたかが分かります。
この禁令のあと様々な模様染が生み出されましたが、これらはいずれも糊防染もしくは部分彩色といった技法で描かれていて、これは現代の染色技術と基本的には同じでした。また、この頃にはすでに現在のファッションブックに類する「衣裳雛形本」も数多く刊行されていたのですが、その中で「友禅模様」という柄が当時爆発的流行を見ました。この「友禅模様」とはその頃人気のあった扇絵師・宮崎友禅の扇絵を小袖の柄に応用したものでしたが、実はこの模様をやはり当時としては最新の糸目糊置き・色挿しの技法で表したものを「友禅染」と呼び、やがてその技法のことのみを「友禅染」と呼ぶようになったのです。
友禅染はその後、染色技法のひとつの主流を成し今日に衣至っています。染めだけで自在な模様表現を可能とした友禅染は、江戸の民衆の圧倒的な支持を得ました。重厚であることだけが美の第一儀でないことを、人々は時代の意識として強く感じたのです。
京都は深い闇を抱いた都市である(1)
「きょおと~大原~三千院~♪」歌にもたくさん唄われている古都、京都。テレビでJR東海のコマーシャルを見ると、五人に三人は京都へ行きたくなるというくらい、女性の方には人気がある所です。皆さんもお好きでしょう。未公開の古寺を散策し、京料理に舌鼓を打ち、しばし悠久の時間に身をゆだねる。京都が好きで好きで、毎年京都に訪れて、京都の事なら地元の方より詳しい、という方もいらっしゃいます。
そんな京都が、今年遷都千二百年を迎えます。京の都の千二百年目を祝い、六月の祝典を中心に一月から十二月まで、官民をあげていろいろなイベントが行われていますので、京都への旅をお考えの方は、今年のうちに行かれることをお勧めします。
ところで、この遷都千二百年。京都ができてから千二百年なのなら「遷都」ではなく「建都千二百年」のはず。確かに一部では「建都」と表現しているところもありますが、正確には「遷都」が正しいのです。どうして「建都」ではなく「遷都」なのでしょうか。
「遷都とは」「都を他の地に移す」こと。つまり「都を移して」千二百年目という事になります。平安時代の前の奈良時代には、平城京(710年~784年)という奈良の都がありました。その奈良から都を移したのが桓武天皇なのですが、平城京が出来たのが794年。つまり平城京と平安京の間には十年間の空白があるのです。歴史に詳しい方ならご存知かと思いますが、実は平安京以前に、京の地にはもう一つの都があったのです。幻の都、長岡京です。
長岡京は、現在でも京都府の南の長岡京市という地名にその名を残しており、史跡は京都府向日市にあります。桓武天皇が最初に作った都は、この長岡京だったのです。しかし長岡京はわずか十年でその幕を閉じます。造営も終わらぬうちに、逃げるように桓武天皇はこの長岡京を捨てたのです。そして新たに作られた都が平安京でした。「遷都千二百年」とは長岡京から平安京に移って千二百年という事なのです。
桓武天皇は何故長岡京を捨てたのでしょう。この時代、権力闘争は、血を血で洗う凄惨なものでした。殺し殺され、保身のためなら身内でも殺しあったのです。勝者はつねに犠牲になって非業の死を遂げた、恨みをのんで死んでいった亡者の亡霊に怯えていました。当時は怨霊の存在が強く信じられていたのです。桓武天皇は怨霊から逃れるために、造営中であったのにもかかわらず、長岡京を捨て、新たに平安京を作ったのでした。
つまり、こういう事になるのです。今年遷都千二百年を迎える京都では、じつは怨霊に追われて急いで建設された都だったと。上御霊神社、下御霊神社、北野天満宮、白峰神社。いくら京都が詳しい方でも、この四つの神社の共通項がわかる人がそういないと思います。これらの神社こそ、都の歴史の闇の部分を封じ込めた空間なのです。
京都は深い闇を抱いた都市である(2)
■呪われた遷都 -遷都は「呪い」という形で行われた-
781年、光仁天皇の譲位により、山部親王が即位する。平安遷都を行う桓武天皇の誕生である。山部天皇には政敵がいた。腹違いの兄弟にあたる他戸(おさべ)親王である。実は770年に光仁天皇が即位したときには、この他戸親王が次期皇太子になるはずだった。光仁天皇には4人の王子がいて、他戸は王位継承順位からいえば最下位だった。しかし当時朝廷には天智、天武という反目する2つの皇族の流れがあり、天智派の光仁天皇が即位するためには、天武の流れをくむ他戸親王を次期天皇の位につけておく必要があったのだ。ところが山部擁立を企てる謀臣達が、他戸親王とその母井上皇后に謀反の疑いをかけ失脚させたのである。さらに光仁天皇を呪い殺そうとしたという罪ををきせ、2人を配流してしまうのだが、これは山部親王本人の意志ではなく、徹底した皇統を狙う天智派の陰謀であった。
無実の罪に問われた他戸親王と井上皇后は、この恨み末代まで祟れよと呪いながら、配流の地で同日同時刻共に殺されてしまう。天皇に即位した桓武は、この2人の祟りを恐れ、都を平城から長岡へ移すことになる。桓武天皇の、怨霊から逃れようとして行った「呪われた遷都」は、こうして始まったのである。
平城京遷都の理由については、考古学的に見た場合、例えば立地条件から来る水陸交通の不便さ、当時台頭していた仏教界への政治介入の断絶、皇位継承問題や藤原氏の陰謀説など、様々な要因があったようですが、その根底には古代人が共通して持っていた怨霊や祟りといったものに対する、観念的畏怖心があるようです。怨をだいて死んだ者の怨霊を恐れこれを祀って祟りをまぬがれようとする意識は、古代の人々の考え方や行動意識をを定義づけ、平安時代になると怨霊を祀る御霊信仰という信仰形態の確立を見ます。
京都は深い闇を抱いた都市である(3)
■呪われた都・長岡京
奈良の平城京から都を移し、新たな長岡京の造営が始まった翌年の延歴4年、桓武天皇の腹心で長岡京の建設を任されていた造宮使、藤原種継(たねつぐ)が何者かに暗殺されるという事件が起こった。のちの調べで大伴、佐伯両氏の陰謀と分かったが、その首謀者の一味に桓武天皇の弟で皇太子となっていた早良親王が関係していたのではないかという疑惑が持ち上がった。早良親王は否定し身の潔白を主張したが身柄を拘束されてしまう。実は桓武天皇には一人息子の安殿(あて)親王がいた。桓武としては自分の息子に継がせたかったのだが、天皇継承順位で行けば早良新王が次期天皇になってしまう。つまり桓武にとって早良新王は邪魔な存在だったのだ。その親王に謀反の疑いがかかった。もはや桓武にとって早良新王を失脚させるには、謀反の「疑い」だけで十分であった。
親王はただちに長岡京の乙訓寺(おとくにでら)に幽閉されてしまう。無実を訴える親王は、そのときから自ら一切の飲食を断ち、命を賭けて身の潔白を主張したが、ついに淡路へ送られる途中で餓死してしまう。
皇太子の尋常でない死は、当然桓武天皇に怨霊の恐怖を抱かせる。案の定、天皇の身辺に祟りとしか考えられないような事件が起こり始めた。まず788年(延歴7年)に夫人の旅子(たびこ)が30歳の若さで死に、翌年には天皇の母の高野皇太后が、またその翌年には皇后の乙牟漏(おとむろ)が31歳で亡くなった。さらにその翌年の791年(延歴10年)には皇太子安殿親王の心身異常が続いた。陰陽師(おんみょうじ=人々に呪いをかけたり解き放ったりする呪術を扱う職業のこと。元々は天文、方位、相地といったものを司っていた)の占いによれば、早良新王の祟りによるものであるという。
怨霊におののく桓武天皇は、早良新王の霊に謝してみたものの、恐怖は鎮まることがない。桓武に残されたのは、怨霊のうろつく長岡京から他の地に遷都するしかなかった。793年(延歴12年)正月、長岡京の造営が始まってからまだ10年というのに、新都となる山背国葛野(やましろのくにかどの)の地の視察が行われた。そして翌年の10月28日、ついに遷都の紹が下されたのであった。
人々はこの新都を、異口同辞に”平安京”と呼んだ。新京の名は唐の長安を意識したものであったろうが、その背景には怨霊から逃れたい桓武天皇の祈りがあったのである。
京都は深い闇を抱いた都市である(4)
■平安京遷都
794年(延歴13年)、桓武天皇は長岡京から山背国葛野郡宇太村(やましろのくにかどのぐんうたむら)の地に遷都する。そして山背国を山城国と改め、新都「葛野大宮」を「平安京」と名付けた。新京の地は、左右と背後に山を配し、南面に平地が開けている。これは道徳の教えによる「四神相応」という考え方に基づいて場所が選ばれている。つまり青龍、白虎、朱雀、玄武という四つの想像上の動物が都を守るというもので、それぞれが東西南北を守り固め、悪霊の侵入を防いでいるのである。
四神 玄武-北 舟岡山
青流-東 鴨川
朱雀-南 小倉池(巨椋池)
白虎-西 山陽山陰に続く大きな道
怨霊を恐れ、怨霊から逃れることを望んだ桓武にとって、平安京は理想的な地形だったのである。またそれ以外にも、平安京には霊的なものの侵入を防ぐ様々な仕掛けが施されている。たとえば平安京の条坊(市街)は三方を山に囲まれているが、唯一南だけがひらけている。そこで京域の南端の羅生門には、それをはさむように東寺と西寺を配し、鬼が入るのを防いだ。また、東寺の鬼門にあたる屋根の鬼瓦には、五芒星と呼ばれる形が刻まれている。鬼門とは、陰陽道で鬼が出入りするとして忌み嫌う東北の方角の事で、五芒星とは陰陽師が呪術に用いる、悪魔祓いの力があるとされる形である。御所の鬼門は四角に削られて、その上には猿が御紋を掲げて飾ってある(現在でも京都の町では建物の鬼門の方角に塩が盛られているのが見受けられる)。そして最後の仕掛けとして、鬼が住むと信じられていた比叡山(平安京の鬼門)に延暦寺を建てたのである。平安京は、まさしく怨霊から逃れるために造られた都なのであった。
804年(延歴13年)、桓武天皇は重い病気にかかった。僧侶150名が宮中へ呼ばれ病気平癒の祈祷をしたが、二年後の延歴15年、ついにかつての政敵たちとの怨霊に怯えながら、一つの遺言を残して70歳で崩御した。「早良親王を祀り続けよ」と。
桓武天皇は、早良親王に死後「祟道天皇」の名称を与えている。天皇に位を上げ、祟りを鎮めようとしたのである。そしてこの祟道天皇をはじめ、平安京に災いをもたらした8人の亡者の怨霊をなだめるための、彼らを祀る神社が建立された。それが上御霊神社なのである。
京都は深い闇を抱いた都市である(5)
■怨霊の棲む都
京都御所から北の、静かな住宅街の一画。何の変哲のないところに上御霊神社はある。この「御霊」とは怨霊のこと。実はこの上御霊神社と下御霊神社、北野天満宮、白峰神社はみな怨霊を祀った神社である。恐ろしい祟りを封じ込めた場所といってよい。この両御霊神社には崇道天皇(謀反の罪に問われ淡路島に流された早良親王)、政敵だった井上皇后、他戸親王など8人の霊が祀られている。みな権力闘争の犠牲となり、非業の死を遂げた者たちだ。北野天満宮。学問の神様、菅原道真で有名なこの社もはじまりは怨霊鎮めの神社であった。醍醐天皇と藤原時平の失脚に遇い、恨みをのみながらかの地で没した道真の怨霊を鎮めるための、ふたたび「天満自在天神」として祀ったのだ。
御所北側の今出川通りにある白峰神社は、小さいながらも明治神宮などの大社と同じ「神宮」という格式を持った社。ここに祀られているのは平安末期の崇徳院、崇徳天皇。この怨霊は凄まじい。流刑の地で精魂を尽くし書き上げた写経の奉納を後白河に拒否され怒り絶望した崇徳は、この上は日本国の大魔王となり、果てしない災いをもたらそうぞと呪いの誓文を己の生血で書き記し、生きながら悪鬼天狗の姿となって怨念を凝らしたという。ところでこの白峰神社を創建したのは明治天皇である。つまり歴史上で最も恐ろしいこの怨霊は、この時まで七百年にわたって都に暗い影を落としていたことになるのだ。
遷都69年後の貞観5年(863年)、怨霊の暗い影を払うため、大内裏の神泉苑で怨霊鎮めの御霊会が行われた。それは明るい光の元で繰り広げる盛大な「まつり」であった。祇園祭も御霊会にはじまり災いを鎮めるためのものであった。平安後期になると都に疫病が大流行する。この狭い盆地に屍が累累したという。死者たちは洛外の鳥辺野や蓮台野などに葬られた。その鳥辺野の入り口に当る無常所(墓場)、六道珍皇寺。
普段は何の変哲もない寺だが、8月8日~10日の3日間だけ高野槇を買い求め、六道の迎え鐘をつく人でたいへん賑う。冥途まで届くという鐘で精霊を迎えるのだ。この精霊を再びあの世に送り返すのが五山の送り火、いわゆる大文字である。平安京は町そのものが、ひとつの大きな無常所なのだ。
権謀術数渦巻く都、京都。雅やかなたたずまいの陰で、都の歴史の闇を封じ込めた空間は、現在も脈々と息づいている。今は静かな怨霊たちも、あるいはひそかに出番をうかがっているのかもしれない。
昔むかしの緑区・青葉区・都築区
今から二百年前、もちろん貴方はいらっしゃいませんでした。しかし、貴方がお住まいのその場所は二百年前の江戸時代からありました。今回は江戸時代の私たちの町のお話です。
昔むかし、今の緑区、青葉区、都筑区の辺りは、武蔵野国都筑区といわれました。江戸時代の地誌「新編武蔵国風土記稿」(文政11年・1828年)によると、今の三つの区の地域には長津田村・恩田村・石川村など、四十一の村があったそうです。今日、世帯数二一万を数えるこの地域も、江戸の頃は僅か四十一の村が山や谷戸や雑木林の中に点在するだけで、風土記によれば「家屋折々散在す。陸田多く水田少なし。全て天水を用いる地なり…」という寒村だったようです。都築郡の北の端は今の都築区で、ここには十三の村がありました。北の方から山田村・牛久保村・茅ヶ崎村・大棚村・勝田村・荏田村・東方村・川向村・大熊村・池辺村・佐江戸村・川和村で、今日の町名が昔の村の名からきていることが分かります。このうち川和村は、徳川二代将軍・秀忠の夫人、崇源院の領地だったといわれています。また今の茅ヶ崎南五丁目付近には、その昔「茅ヶ崎富士」とよばれる小高い丘があり、絶景を博していたそうです。
一方、青葉区には江戸時代、十六の村がありました。青葉台周辺は恩田村で、ここからは青葉台をはじめ田奈、しらとり台、つつじが丘、あかね台など十四の町が生まれました。聞いたところによると、青葉台駅の辺りはその昔は谷戸で、狸やイタチの棲み家だったそうです。また、あざみ野や美しが丘、すすき野にかかる広い一帯は石川村といわれ、都筑郡の中でも戸数267件を有する一番大きな村で、ここには京都の天皇の牧場(?)があったと伝えられています。青葉区役所のある辺りは今も同じ名の市が市ヶ尾村。ここは昔から今の国道246号線にあたる大山街道と、上麻生線にあたる日野往還が交差していた交通の要所で、幕末には区役所近くに二件の旅籠があり、その古い建物はつい十年ほど前まで現存していたそうです。三区の中でも比較的古くからの町並みが残っているのが緑区。江戸時代には十四の村がありました。鴨居村や十日市場村など、やはり当時の地名をそのまま引き継いでいるところが多いようです。なかでも長津田村は大山街道の宿場町として、当時はたいそうな賑わいをみせたそうです。そんな都築郡も、二百年の時の流れの中で大きく変わりました。しかし現在の町の姿も、長い長い歴史の流れの、ほんの一コマに過ぎません。そして今から二百年後も、この町は存在している(ハズな)のです。二百年後の私たちの町、一体どうなっているのでしょう。
資料:みどり新聞 2月25日号

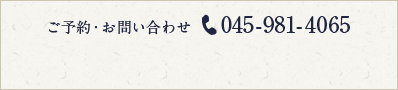



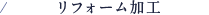
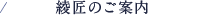
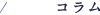



.jpg)